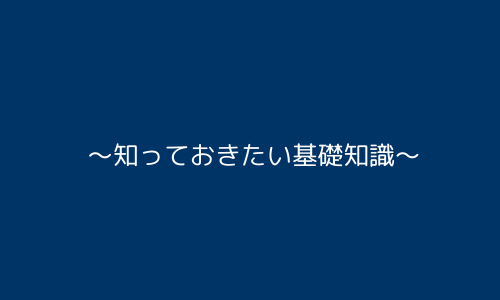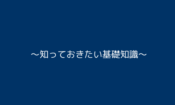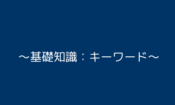障害年金受給のための3つの条件
では続いて、障害年金を受給するための条件についてお話しします。
障害年金を受給するための要件として、大きく3つあります。
一つ目は、制度加入要件、二つ目が、保険料納付要件、そして三つ目が障害状態要件です。
そして、これらの全ての要件を満たす必要があります。
<障害年金の3要件>
障害年金を受給するためには、次の3つの条件すべてを満たすことが必要です。
① 制度加入要件
初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金保険など)のいずれかに加入していること。
② 保険料納付要件
年金の保険料を一定期間以上納付していること。
③ 障害状態要件
障害等級に該当する程度の障害状態であることが主治医の診断書等により判断できること。
まず、制度加入要件です。
制度加入要件は、初診日時点で、国民年金や厚生年金保険などの年金制度に加入していたかどうかを判断するものです。
初診日時点で、国民年金や厚生年金保険などの年金制度に加入していたことが必要です。
しかし、例外として、初診日に年金制度に加入していない場合でも障害基礎年金の対象となる場合があります。
具体的には、初診日が、年金制度に加入義務のない20歳前にある、もしくは、60歳以上65歳未満にあり国内に居住していた場合に要件を満たします。
初診日という言葉が何度か出てきましたが、実はこの初診日の証明をすることができずに、障害年金の受給を諦めざるを得なかったというかたが多くいらっしゃいます。
この後も初診日の話がたくさん出てきますが、障害年金では、この初診日の証明ができるかどうかが非常に重要になってきますので、覚えておくようにしてください。
そして2つ目は、保険料納付要件です。
年金制度は年金保険制度です。
保険制度ですので、保険料の支払いを適切に行っている必要があります。
したがって、年金の保険料を一定期間以上納付している、もしくは、免除などの正しい手続きを行っている必要があります。
最後に、障害状態要件です。
障害等級に該当する程度の障害状態であることが、主治医の診断書などによって判断できることが必要となってきます。
はじめの方でご説明したとおり、障害年金は病名で判断するものではありませんので、一定の重さ、障害状態に該当している必要があるということになります。
初診日とは?
ではここで、初診日についてもう少し詳しくお話しします。
<初診日>
•障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師等の診察を受けた日。
•初診日における年齢や加入していた制度により、障害年金が受給できるかどうか、「障害基礎年金」が受給できるのか、「障害厚生年金」が受給できるのかが決定されます。
•知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
まず、そもそも初診日とはいつのことを言うのかですが、障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師などの診察を受けた日のことを言います。
一般的にはその医療機関を最初に受診した日のことになるかと思いますが、障害年金では、原因となったご病気全体を通して最初に診療を受けた日となります。
つまり、障害年金の初診日は、たくさんの病院を受診していても、基本的には病気や怪我ごとに一つしかないということになります。
そして、初診日における年齢や加入していた制度により、障害年金が受給できるかどうか、また、障害基礎年金が受給できるのか、障害厚生年金が受給できるのかが決定されますので、初診日は非常に重要なものになります。
また、初診日は障害年金の権利発生を左右する重要なものですので、障害年金の審査では、非常に厳密に初診日の審査が行われます。
なお、障害年金の初診日には一つ例外的な取扱いがあります。
それは、手続きする傷病が知的障害の場合は、初診日は出生日、つまり誕生日となります。
仮に、最初に病院を受診したのが12歳の時であっても、誕生日が初診日になるということです。
これは、知的障害が先天性の傷病であることに起因するためですが、数多くの先天性疾患がある中でも、この初診日の取り扱いが行われるのは知的障害だけになります。
その他の先天性疾患では、本来通り初めて医師の診察を受けた日が初診日となりますのでご注意ください。
初診日の証明はどう行う?
次に、初診日の証明についてお話しします。
<初診日の証明>
•初診日は受診状況等証明書もしくは診断書を取得して証明を行います。
•カルテは、受診終了後5年間の保存が義務づけられています。
•治療歴が長いとカルテが廃棄されている場合や閉院していることが多く、初診日の証明が困難に。
•証明書が取得できない場合でも客観的・合理的な資料を提出することで初診日が認定される可能性があります。
初診日はどのようにして証明を行うのかですが、初診日は、医師が作成する受診状況等証明書という書類、もしくは、診断書によって証明を行います。
証明書や診断書の記載内容を元に、初診日の審査が行われるということになります。
しかし、実際の手続きを進める際には、この初診日の証明ができずに困ってしまうケースがあります。
それは、医療機関におけるカルテの保存義務が5年間であるということが大きく影響しています。
障害年金の手続きを行うかたが、病歴が5年以上となることは決して珍しくありません。なかには30年前に初診日があるというかたもいらっしゃいます。
このように治療歴が長いと、初診の病院でカルテが破棄されてしまっていたり、病院そのものが閉院してしまっていることが多く、その結果、初診日の証明がとても困難になってしまうということがよくあります。
年金制度上、初診日がわからないと、要件を満たしているかどうかの判断ができず、障害年金の認定の対象とならなくなってしまうことがあるというのが、障害年金を請求するうえで難しいポイントになります。
しかしながら、証明書が取得できないという場合でも、客観的・合理的な資料を提出することで、初診日が認定される可能性はあります。
ですので、初診病院のカルテ破棄や閉院で証明書の取得ができないと絶対ダメということはありませんので、諦めずに初診日を証明できる方法を探していく必要があります。
保険料納付要件とは?
続いて、保険料の納付要件についてもう少し詳しくお話しします。
<保険料納付要件>
•初診日がある月の2ヶ月前までで、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付されている、または、免除されていることが必要。
•(上記の要件または)初診日がある月の2か月前までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと。
•20歳前傷病では保険料納付がないため、納付要件は問われません。
先ほども少しお伝えしましたが、障害年金制度はあくまでも保険制度です。ですので、保険料の支払いを適切に行っている必要があります。
では、具体的に、どの程度保険料を納めている必要があるのかについてお話しして行きます。
保険料の納付に関して、2つの要件があります。
どちらか一方を満たしていればOKということになっています。
まず、基本の要件です。
初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付されている、または、免除されていることが必要です。
ここで重要なのは、この保険料納付要件は、初診日の前日時点での納付状況や免除の状況によって判断が行われるということになります。
もし、初診日以後に過去の保険料の支払いや免除の手続きを行っている場合には、この保険料納付要件を判断するにあたっては、未納扱いとなってしまいます。ですので日頃から、期日までに適切な納付や手続きを行っていくということが、非常に大切なことになります。
そして、もう一つの要件ですが、初診日において、初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納期間がないことです。
こちらに該当する場合には、過去にどれだけ未納期間が続いていたとしても、直近1年間に未納期間がなければ、障害年金を認めてあげましょう、というものになります。
この2つの要件のうち、どちらかに該当していれば、この保険料納付要件を満たしていることになります。
国民年金の加入は20歳になってからです。
それではもし、初診日が20歳前にあった場合には、保険料納付要件はどのように判断されるのかということについてですが、20歳前は国民年金への加入義務がありません、つまり、保険料の納付ということも発生しません。
したがって、そもそも保険料納付要件は問われないということになります。
障害状態要件とは?
次に、障害状態要件についてもう少し詳しくお話しします。
障害状態要件というのは、障害の状態が等級に該当するだけの状態である必要があるということです。
そして、障害状態要件を確認するにあたって大切なのは、障害認定日というものです。
<障害認定日とは?>
•障害認定日とは、障害の状態の認定を行う日のこと。
•初診日から1年6か月を過ぎた日
•障害認定日の例外
18歳6か月以前に初診日がある場合、障害認定日は20歳の誕生日の前日
•障害認定日以降から障害年金が請求できます。
障害認定日とは、障害の状態の認定を行う日のことを言います。
具体的に障害認定日がいつかというと、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日のことを言います。
ただし、傷病や障害の状態によっては例外があります。
この場合は、1年6ヶ月経過日よりも前に障害認定日が来ることもあります。
また、初診日が18歳6ヶ月以前にある場合には、障害認定日は一律に20歳の誕生日の前日となることになっています。
障害認定日以後に障害等級に該当していると、この障害状態要件を満たすことになります。
したがって、障害年金は、障害認定日以降から請求手続きが可能になるということになります。
障害等級の目安は?
それでは、障害年金の等級は、 1級から3級までありますが、それぞれどんな状態のことを指すのかについて述べます。
<障害等級の目安>
•障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態
•障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態
•障害の程度3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とするほどの障害の状態
•障害認定基準によって等級判断が行われます
これから、等級の考え方の目安について見ていきたいと思います。
まず、障害等級1級です。
他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態、というのが障害等級1級です。
生活の範囲がべットに限られるような状態と表現したりもします。
次に、障害等級2級です。
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくとも、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害状態、というのが障害等級2級です。
生活圏が自宅内に限られてしまうような状態と表現したりもします。
そして、障害等級3級です。
労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とするほどの障害の状態、というのが障害等級3級です。
安定した就労を行うことが難しい状態といったイメージになります。
今お話ししたのは、各等級の目安、大まかなイメージです。
実際には、障害認定基準というもので、傷病ごとの特性に応じて細かく基準が定められていて、その基準で等級の判断が行われます。
この基準を理解することはかなり難しいかもしれませんが、ご自身が該当する部分だけでも一読しておくと、手続きを進める上で参考になるかと思います。
詳しくは、日本年金機構のホームページから閲覧をしてみてください。
精神疾患の場合の認定基準とは?
ここで、障害年金の請求を行うかたがとても多い、精神のご病気について、もう少しこの認定基準について掘り下げてみたいと思います。
例として、精神疾患による障害年金の2級の認定基準がどのようになっているのか見ていきましょう。
精神の認定基準では、病気の種類によって、それぞれどのような状態が2級に該当するのかが記載されています。
その中でも、知的障害、発達障害、気分障害についてご紹介をいたします。
<精神2級の認定基準>
・知的障害
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
・発達障害
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
・気分障害
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
まず、知的障害についてです。
知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの。
次に、発達障害についてです。
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。
そして、気分障害についてです。
具体的な病名で言えば、うつ病、双極性感情障害、気分変調症などが該当してきます。
気分・意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、または頻繁に繰り返したりするため、日常生活が一時的に制限を受けるもの、このように記載されています。
先ほどの大まかな基準よりも、それぞれの傷病の特性が反映された内容となっています。
もちろんこれは、ごく一部を抜粋したものになりますが、このように、傷病ごとに基準の定義が行われています。