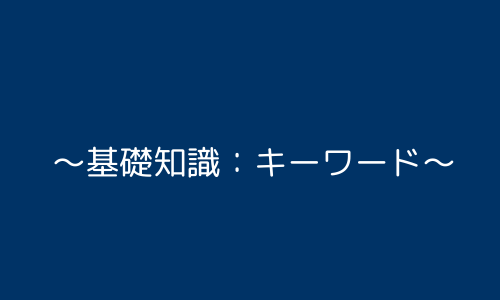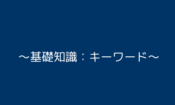第三者証明
カルテが廃棄されていること等により、初診時の医療機関で初診日の証明が得られないことがあります。
このような場合、第三者証明(医療機関で診療を受けていたことについて、第三者が申し立てることにより証明したもの)により初診日を証明する方法があり、文書によって行われます。
<初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)>
「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」は、初診日の頃の受診していた状況を、第三者(三親等以内の親族は除く)が証明したもので、複数の第三者証明を添付すると、初診日を裏付ける書類として扱ってもらえます。
第三者に当てはまるのは、隣人、職場の上司、同僚、民生委員、病院長、施設長、事業主などです。
なお、民法上の三親等以内の親族による第三者証明は認められていません。(いとこは四親等となりますので第三者になります)
第三者証明は、原則として、複数名から取得することが求められますが、当時を知る医療従事者(当時の担当医や看護師等)であれば、単独の証明でも有効とされます。
第三者証明は、以下の3つのいずれかに該当することが必要です。
申立者が請求者の受診状況を
①初診日当時に見て知った
②初診日当時に聞いて知った
③初診日当時ではないが、今から5年以上前に聞いて知った
<第三者証明で求められる証明内容>
次のような事項について詳細を記載することが求められています。
・ 発病から初診日(または20歳前)までの症状の経過
・ 初診日頃(または20歳前)における日常生活上の支障度合い
・ 医療機関の受診契機
・ 医師からの療養の指示など受診時の状況
・ 初診日頃(または20歳前)の受診状況を知り得た状況 など
<第三者証明による初診日の認定>
第三者証明を提出すれば必ず初診の証明ができるというものではありません。
記載内容や他の資料との整合性を踏まえて総合的に判断され、初診日が認定されます。
20歳以降に初診日がある場合は、第三者証明単独では初診日が認められないため、診察券や入院記録などの、初診日について客観性が認められる他の参考資料の提出も必要となります。
1.初診日が20歳以後の場合
・障害年金の種類が複数 → 加入制度の特定が必要
・第三者証明+他の資料(客観的なものであること)→ 整合性+総合判断
2.初診日が20歳前の場合
・障害年金の種類は単一
・第三者証明のみでも総合判断により初診日の認定が可能とされています