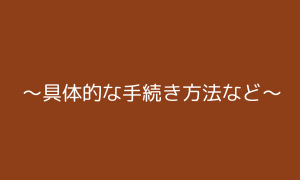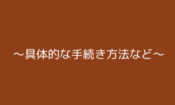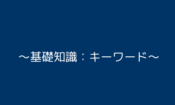STEP3:初診日の確定(証明)
初診日を明確化し、保険料納付状況を確認することができたら、次に、初診日の証明をとります。
初診日の証明は、原則として、カルテに基づいて記述される医師による証明(医証)、具体的には、「診断書」または「受診状況等証明書」によって行われます。
以下のとおり、初診の医療機関と診断書を作成してもらう医療機関が同じかどうかにより、受診状況等証明書を取得する必要があります。
①初診の医療機関と診断書を作成してもらう医療機関が同じであれば、診断書によって初診日を証明することができるため、受診状況等証明書は不要です。
②初診の医療機関と診断書を作成してもらう医療機関が異なる場合は、初診日に受診した医療機関で受診状況等証明書を作成してもらいます。
Action:上記②の場合、受診状況等証明書の様式を用いて、初診の医師にお願いしてください。
上記のとおり、障害年金の請求については、受給要件を満たしていることを確認するために初診日を明らかにする書類(「受診状況等証明書」などの医療機関の証明書)の添付が必要です。
しかし、カルテの法律上の保存期間は5年間であるため、終診(転医)から5年を経過していると、当時のカルテが廃棄されていること等により、初診時の医療機関におけるカルテに基づく初診日の証明が得られないことがあります。
初診の医療機関にカルテがない時には、次に受診した医療機関で受診状況等証明書を作成してもらうことになります。
しかし、初診日がかなり前のケースでは、次に受診した医療機関でもカルテが廃棄されていることもあります。
このような場合、さらに次に受診した医療機関で受診状況等証明書を作成してもらうことになります。(以下、初診日が確認できるまで繰り返します)
なお、受診状況等証明書が取得できない場合は、取得できない医療機関ごとに、受診状況等証明書の代わりとなる「受診状況等証明書を添付できない申立書」を請求者が作成することになります。
また、初診日を明らかにする参考資料がある場合には、それらを添付します。
Action:医療機関によっては5年より長い期間保存していることもあるので、まずは医療機関に確認してみましょう。
なお、2番目以降に受診した医療機関で受診状況等証明書を取得する場合、その証明書が初診日の証明として有効となるには、請求の5年以上前にカルテが作成されていて、そのカルテに本人が1番目の医療機関の初診日について話した記録があることが必要です。
また、1番目の病院の紹介状が添付されていることでも、証明として有効となります。
最終的に、受診状況等証明書を入手できなかった場合は、第三者証明などの参考資料により証明する必要があります。
参考資料によって初診日を特定できたり、初診日の前後の日付を特定できたりすることがあります。あきらめずに初診日に関する参考資料をできる限り集めましょう。
具体的には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に理由などを記入して、次の参考資料を添付します。
<参考資料の例>
- 第三者証明
- 診察券(診療科や診察日がわかるものが望ましい)
- 入院記録
- 次の病院への紹介状
- 医療機関や薬局の領収書
- お薬手帳
- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
- 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
- 障害者手帳の申請時の診断書
- 交通事故証明書、交通事故の載っている新聞記事
- 労災の事故証明書
- 医療情報サマリーや入院治療計画書など(病院が作成した治療経過などを要約したもの)
- 事業所等の健康診断の記録
- 小中学校の健康診断記録・成績通知表(先天性の傷病の場合の参考)
- 母子手帳
- 健康保険の給付記録や診療報酬明細書
- 臨床調査個人票(難病医療費助成を都道府県へ申請するときに添付しているもの)
- 救急傷病者搬送証明書(救急車で搬送された場合など、消防署などで交付)
- 生活保護台帳
第三者証明による初診日の認定
医療機関で初診日の証明が取れない場合、平成27年10月より、第三者による証明が広く認められるようになりました。
第三者証明による初診日の認定は、以前は、20歳前障害による請求に限って認められていましたが、20歳以後の場合にも拡大されています。
20歳以後の場合には、第三者証明のほかに、客観的な他の資料の提出が必要となります。
<初診日が20歳前>
・第三者証明のみでも総合判断により初診日の認定が可能とされています
<初診日が20歳以後>
・第三者証明+他の資料(客観的なものであること)により、整合性と総合判断により認定されます
第三者証明には、以下の3つのパターンがあります。
第三者証明を行う人が、
1.初診日ごろに見て知った
2.初診日ごろに聞いて知った
3.初診日ごろではないが、今から「5年以上前」に聞いて知った
第三者証明は、原則として、複数名から取得することが求められますが、当時を知る医療従事者(当時の担当医や看護師等)であれば、単独の証明でも有効とされます。
なお、これまでと同様に、民法上の三親等内親族による第三者証明は認められていません。
第三者証明で求められる証明内容
第三者証明では、次のような事項についてできるだけ詳しく記述されていることが大切です。(具体的なエピソードなどが入っていると良いです)
- 発病から初診日(または20歳前)までの症状の経過
- 初診日頃(または20歳前)における日常生活上の支障の度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃(または20歳前)の受診状況を知り得た状況 など
初診日が一定期間内にある場合の初診日の認定
初診日が一定の期間にあることまではわかっているけれど正確には特定できない場合、初診日がある一定期間の始まり(始期)と終わり(終期)を立証して、その間の保険料納付要件が充足されていれば、本人申立日が初診日として認定されます。
なお、一定の期間に加入していた年金制度が単一かどうかで取扱いが異なります。
一定期間内に、国民年金と厚生年金の(年金制度が単一でない)加入期間があり、本人が申し立てる初診日が厚生年金の加入期間にある場合には、一定の期間の始期と終期を示す参考資料のほかに、本人申し立ての初診日についての参考資料(第三者証明など)の提出も必要となります。
初診日を特定できる資料が取得できなくても、あきらめずに初診日の前後を明確にできる資料を集めてみてください。