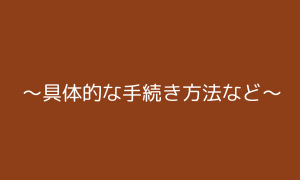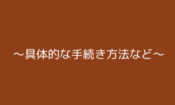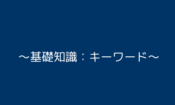STEP8:受給開始後の手続き等
障害の状態は変化する可能性があるため、障害年金の給付が開始されたとしても、そのまま生涯にわたって障害年金を受給できるとは限りません。
障害年金は、「永久認定」以外は、一定期間ごとに審査を受けなければなりません。
障害年金の認定には、一度認定されれば更新手続きが不要な「永久認定」、定期的な更新手続きが必要となる「有期認定」があります。
どちらの認定になるのかは、認定医が、傷病の特性や障害状態の変動の可能性などにより個別に判断します。
<障害年金の認定>
①永久認定
・足の切断などの欠損障害など、これ以上軽傷に変わることがない障害が対象
・「次回診断書提出年月」欄が「**」となっています。
・永久認定された場合でも、障害の状態が増悪した場合には、額改定請求を行うことはできます。
②有期認定
・精神障害や内部疾患のように、障害状態が変わることがある障害の場合
・有期認定となった場合は、1年〜5年に一度、更新手続きが必要です。
更新手続き
具体的には、決められた期間ごとに「障害状態確認届(診断書)」の「診断書」欄を医師に記載してもらい、年金機構に提出します。
障害年金の決定通知書(年金証書)には、「次回診断書提出年月」が記載されています。通常は、数年後の誕生月を指定されます。
次回診断書提出年月の3ヵ月前の月末ごろに、「障害状態確認届」の提出依頼通知が届きます。
提出するのは、障害状態確認届の用紙と一体となった診断書で、内容は、初回の障害年金申請時に提出した診断書とほぼ同一です。(誕生月の末日以前3ヵ月以内に受診をした診断書を提出します)
また、誕生月の末日までに提出が必要ですので注意してください。
障害等級の再認定は診断書のみで行われるため、診断書の記載内容が非常に重要となります。
障害状態確認届を提出する前に、必ず診断書の内容をチェックしましょう。
再認定の結果、減額改定されてしまったり、支給停止となったりすることもあります。
障害の程度が実際に軽くなっているのであればよいのですが、実態より軽度に受け取られるような記述がされていることもあります。
診断書の記載内容によっては、医師に訂正や加筆を依頼する必要があります。
特に、転院や医療機関の人事異動等で主治医が変わったときには、障害の状態が変わらなくても診断書の記載内容が変わることも多いので、注意してください。
等級の見直しで年金額が減額改定された場合や支給停止になった場合に、決定された等級や内容に納得がいかないときには、不服申立てをすることができます。
通知を受け取った日の翌日から3ヵ月以内に、審査請求の手続きを行うことになります。
支給停止された場合
障害年金の等級の見直しによって支給が停止された場合、その後、障害の状態が増悪したら年金の支給の再開を求めることができます。
このような場合、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」を提出します。
その際、支給停止の事由が消滅した証拠書類として、医師の診断書の添付が必要です。
この請求が認められた場合、支給停止事由が消滅した日(診断書の現症日)の翌月分から年金の支給が再開されます。
重症化した場合
障害年金2級または3級を受給している方が、障害の程度が重くなり、1級または2級に該当するようになった場合には、額改定の請求をすることができます。
額改定の請求は、請求を行うことができる時期について、①障害年金を受給する権利を取得した日から1年を経過した日以降、あるいは、②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日以降と決められています。
なお、障害状態確認届を提出して同じ等級と確認された場合は、上記②でいう「障害の程度の診査を受けた日」に該当しませんので注意してください。
額改定の請求は、「障害給付額改定請求書」に、請求日以前3ヵ月以内の診断書を添えて行います。
なお、障害の程度が上位等級に該当することが、診断書から確認できる必要がありますので、診断書の内容は、必ずチェックすることが大切です。
障害給付額改定請求書を提出する前に、必ず診断書の内容をチェックしましょう。
請求の結果、現在受給している等級より上の等級に認められると、請求書を提出した月の翌月から、年金額が改定されます。
3級の障害厚生年金を受給している方が、一度も2級以上に該当しないまま65歳にななった場合、その後に障害の状態が重症化しても、額改定請求をすることはできません。(65歳の誕生日の前々日まで請求可能)
障害の状態が重症化したと感じた場合は、早急に額改定の請求を行うことが大切です。