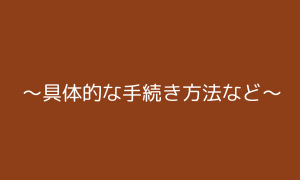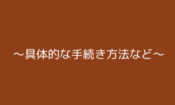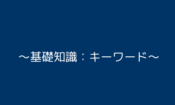STEP4:診断書の取得
初診日の証明が取得できたら、次に準備しなければならないものは「診断書」です。
障害年金の審査は書類だけで行われ、その結果、支給・不支給が決まります。
その際に、診断書は非常に重要なもので、診断書の内容で結果が決まると言っても過言ではありません。
障害年金の診断書は、以下の8種類の様式があります。
・眼の障害用(様式120号の1)
・聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用(様式120号の2)
・肢体の障害用(様式120号の3)
・精神の障害用(様式120号の4)
・呼吸器疾患の障害用(様式120号の5)
・循環器疾患の障害用(様式120号の6-(1))
・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式120号の6-(2))
・血液・造血器・その他の障害用(様式120号の7)
精神疾患の場合は、「精神の障害用(様式120号の4)」になります。
下表のとおり、請求方法により、診断書に記載してもらう障害状態の時点(現症日※)や枚数が違ってきます。
※現症日とは、その症状がいつの時点のものかを指す日です。

<障害認定日請求>

<障害認定日請求(遡及請求)>

<事後重症請求>

診断書の作成を依頼する際には、診断書用紙を持参して依頼する内容を明確に伝えるようにします。
特に、作成を依頼する診断書の現症日は重要です。
そのほか、診断書を記載する際に参考となる事項については、積極的に伝えるようにしましょう。
Action:医師に診断書の作成を依頼しましょう。
日常生活能力の判定7つの項目
「診断書(精神の障害用)」の記載項目のひとつである「日常生活能力の判定」は、等級決定の目安となる項目で7項目あり、精神の障害年金の診断書では非常に重要視されています。
<日常生活能力の判定7つの項目>
・適切な食事
・身辺の清潔保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬
・他人との意思伝達及び対人関係
・身辺の安全保持及び危機対応
・社会性
下図は、診断書(精神の障害用)の一部を抜粋したものです。(出典:日本年金機構HP)

主治医は、これらの日常生活の7つの場面における制限度合いを、4段階で評価します。
そして、その評価結果により、支給・不支給が大きく左右されます。
このことから、障害年金受給のポイントは、障害の状態、特に、日常生活の状況(日常生活にどのくらい支障があるのかなど)を的確に伝え、それらをいかに的確に診断書に反映してもらえるか、ということになります。
ですので、診察時に、ふだんの生活の様子をありのまま伝えることはとても大切です。
Action:障害年金を請求することを決めたら、診察の時は、なるべく日常生活の様子を伝え、医師に実態を理解してもらうよう努めましょう。
しかし、診察時にはうまく話せなかったり、診察時間が限られていたりすることもあり、主治医に自分の日常生活を伝えることは思っている以上に難しいものです。
また、短い診察時間内に日常生活の様子まで踏み込んで聞き出そうとする医師は、少ないと思います。
このような場合は、ふだんの生活の様子をメモしておいて伝える(または渡す)、診察時に家族に付き添ってもらうなどサポートをしてもらうのも良いと思います。
診断書を受領したら
病院等から診断書を受け取ったら、必ず内容を確認しましょう。
封筒に入れ、完全に封をして渡してくれるかも知れませんが、これを開封して内容を確認しましょう。(開封しても問題ありません)
そして、必ずコピーを取っておくことが大切です。