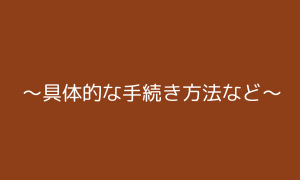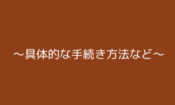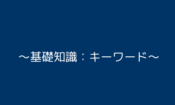STEP7:書類提出後の対応と結果確認等
書類を提出したあとは、審査結果を待つことになります。
多くは3ヵ月くらいで通知が来ます。
また、3カ月を超える場合には、遅れる旨の通知が届きます。
書類を提出してから結果通知が届くまでの間に、「補正」と言って、提出書類の修正や追加の書類の提出を求められることもあります。
また、不備があった場合には、不備の指摘と、その解消の方法を示したうえで、提出した書類が返戻されてきます。
追加書類の提出や不備の解消が早くできれば、結果も早く出ることになりますので、早急に対策を進めることが重要です。
決定通知書は、以下のケースにより異なります。
①支給決定の場合 →「年金決定通知書」
②不支給決定(却下含む)の場合 →「不支給決定通知書」または「却下通知書」
審査の結果、「年金決定通知書」「不支給決定通知書」「却下通知書」のいずれかが、請求人宛てに送られてきます。(普通郵便で届き、宛先は提出時に登録した住所になります)
上記のどの通知の場合であっても内容をきちんと確認し、その後の対応について早急に検討・決定する必要があります。
Action:決定通知書が届いたら、すぐに内容を確認してください。
不支給決定等の場合は、審査請求をするかどうかを早急に決める必要があります。
※社労士などの専門家に相談されることをお勧めします。
<年金決定通知書>
「年金決定通知書」は、障害年金が支給される場合に来る通知です。
この通知が来れば、障害等級の是非は別として、年金が支給されることは確実ということになります。
年金決定通知書を受け取ったら、支給開始年月と年金支給額の根拠等を確認します。
また、障害等級や次回の診断書提出年月等、重要な情報が記載されていますので、それらの内容についても確認してください。
なお、障害の等級が、決定されたものよりも上位等級に該当すると考えて、審査請求を行うことも可能です。
<不支給決定通知書>
「不支給決定通知書」は、障害の程度が法律で定める程度(障害基礎年金を請求した場合は2級以上、障害厚生年金を請求した場合には3級以上)に該当していない場合に送られてくるものです。この通知が届いたら、不支給決定をやむを得ないものとして受け入れるのか、それとも、決定を不服として審査請求をするのかということを、早急に決めなければなりません。
審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から起算して、3ヵ月以内に行わなければなりません。
同時に送付されてくる「決定の理由」を参考に、なぜ不支給となったのか、原因を究明し、その原因に応じた適切な対策を行わなければ、審査請求をしてもまた不支給の通知が来るだけのこととなってしまいます。
対策を講じるための時間も考えると、意思決定は速やかに行うことが重要です。
<却下通知書>
「却下通知書」は、例えば「初診日が確定できない」、「保険料納付要件が満たされていない」等、障害年金を請求する要件が整っていない場合に送られてくるものです。
この場合も、審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から起算して、3ヵ月以内に行わなければなりませんので、「却下」を受け入れるか、決定を不服として審査請求をするのか、早急に決める必要があります。
なお、却下通知についても、「決定の理由」が同時に送付されてきます。
不支給や却下になった場合、支給決定を求めるために以下の3つの方法があります。
①「審査請求」
②「再請求」
③「審査請求」と「再請求」を並行して、または、時期をずらして行う
「審査請求」は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に、地方厚生局内の社会保険審査官に対し行います。
「再請求」は、診断書等が適切な内容でなく再度作成してもらう場合や、病状が悪化した場合に行います。
再請求は、不支給決定を受けてからいつでも行え、一定期間を空ける必要はありません。
ただし、前回の提出から再請求による提出まで短期間であっても、書類はすべて新しく揃えなければなりません。診断書などの病院等の証明書類も、再度取得する必要があります。
なお、「再請求」において、同じ認定日の診断書の内容が、前回提出したものと違っている場合には、その理由について年金機構から問合わせが入る可能性が高いので準備しておきましょう。