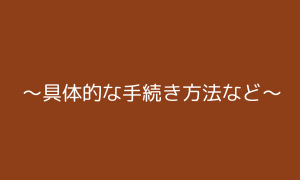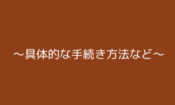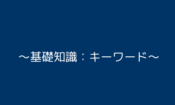STEP1:初診日の仮確定
障害年金の請求手続きでは、最初に初診日の仮確定を行います。
障害年金では、症状が出て初めて病院に行った日を「初診日」と言います。
<初診日の定義>
初診日とは、「障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定義されています(国民年金法第30条他)。
初診日を基準として様々なことが決まっていくので、初診日は障害年金を請求するうえで非常に重要な日になります。
Action:初診日頃(調子が悪いと感じ病院に行った頃)について思い出してみてください。
①症状が出てから最初に行った病院はどこだったか?
②その病院に初めて行ったのはいつだったか?
初めて病院に行った日ならすぐに確認できると思うかも知れませんが、初めて病院に行った日からかなり時間が経っていると、カルテが破棄されていて初診日の証明が困難になってしまうこともあります。
※カルテの法律上の保存期間は5年間です。
また、初診日について誤った認識をされている方も多いので注意が必要です。
例えば、精神の疾患においては、最初に精神科以外を受診するようなケースが多くあります。不調を感じて、まずは内科を受診するというようなことが多いのではないでしょうか。
このようなケースでは、内科を受診した時の疾病と精神疾患が同一疾患とされれば「内科受診の日」が初診日となりますので、注意が必要です。
初診日に加入していた年金制度により、請求できる年金が変わってきます。
初診日によって、受給できるのが「障害基礎年金」なのか、「障害厚生年金」なのかが決まってきます。
年金を受け取るには初診日の前日において、一定の保険料の納付要件を満たしていなければなりません。
また、初診日を基準として障害認定日が決まってきます。
そして、初診日を基準に請求手続きに必要な書類を集めていくことになります。
このように、初診日は、障害年金の受給のための3つの要件などにも密接に関わってきますので、いつが初診日と認定されるかは非常に重要です。
<初診日の証明>
初診日の証明は、原則として、カルテに基づいて記述される医師による証明(医証)により行われます。
具体的には、以下の①または②の書類に、書類を作成した医療機関の受診前に他の医療機関を受診した記述がないことにより証明されます。
①障害年金請求の診断書
②受診状況等証明書 ※初診日の医療機関が診断書作成医療機関でない場合
初診日がわからないなどの場合
初めて医療機関に行った日がかなり前のことで、初診日がいつなのかわからない。
また、転院を繰り返していて初診日の証明が難しいなどの場合は、年金事務所の職員、社労士などの専門家に相談されることをお勧めします。
初診日が明確になったら、次に保険料納付状況を確認します。