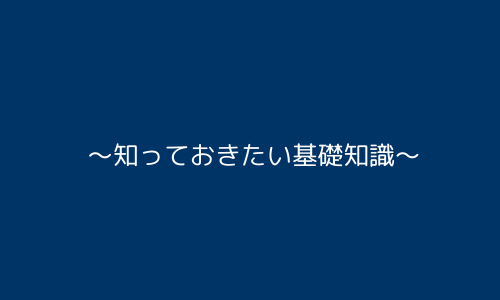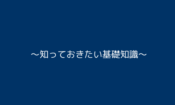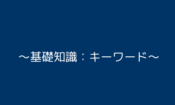障害年金の請求はどうすればよいのか?
次に、請求するにはどうしたらよいのか、ということについてお話しして行きます。
いつから手続きできるのか?
•初診日から1年6ヶ月経過後、もしくは20歳になった時の遅い方以後に手続きが可能です(障害認定日請求)
※傷病によっては、1年6ヶ月経過前に手続きができる場合があります
•障害認定日以後に状態が悪化した場合には、65歳到達前までに手続きが可能です(事後重症請求)
まず、手続きを行うことができるタイミングについてお話しします。
先ほども少しお話しいたしましたが、障害年金は、障害認定日以降から請求手続きが可能となります。
つまり、初診日から1年6ヶ月経過後、もしくは20歳になった時の遅い方に手続きが可能ということになります。
これを障害認定日請求と呼びます。
また、傷病や状態によっては、障害認定日は1年6ヶ月よりも早く来る場合がありますので、そのような場合には、1年6ヶ月よりも早く請求手続きが可能です。
もちろん、障害認定日時点では、まだ等級に該当するような障害状態ではなく、障害認定日からしばらく経ってから、障害状態に該当するような状態に悪化したというケースも多いです。
このような場合には、病状が障害状態に該当するようになってから請求手続きを行います。
これを、事後重症請求と呼びます。
ただし、事後重症請求は65歳に到達するよりも前に、手続きを行う必要があります。
また、障害年金は、過去に遡って受給することができるという話を聞いたことがある、というかたがいらっしゃるかもしれません。
これは、障害認定日時点では障害状態に該当していたのだけれども、当時は障害年金のことを知らず、そのままになってしまい、後から障害認定日時点まで遡って請求手続きを行うというものになります。
年金の時効は5年間ですので、条件に該当すれば、最大5年間分遡って受給することができます。これを訴求請求と呼んだりもします。
3つの重要書類
•受診状況等証明書
•診断書
•病歴・就労状況等申立書
※受診状況等証明書は、対象医療機関から診断書を取得する場合や、知的障害の場合は不要です。
では続いて、障害年金の請求手続きにおいて、特に審査上非常に重要なものとなる3つの書類についてご紹介いたします。
まず、受診状況等証明書についてです。
受診状況等証明書とは、その名の通り、証明書を作成してくださる医療機関の受診状況を証明してもらう書類になります。
初診日を証明・判断するために使用されます。
次に、診断書についてです。
診断書は、請求者の障害状態、つまり、障害等級を判断するための書類になります。
等級に該当するかどうかの判断の大部分を担う書類になりますので、非常に重要な書類となります。
そして、3つ目は、病歴・就労状況等申立書についてです。
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在に至るまでの症状の状況や、医療機関の受診状況、就労状況や日常生活の状況について記載を行うものです。
先にご紹介した受診状況等証明書や診断書と大きく異なる点は、この書類は自分たちで書かなければならないということです。
証明書や診断書は医師が書いてくれますが、申立書は、今までの状況について、要点を整理しながら端的に記載を行い、審査側に状況を伝えていく必要があります。
このため、 この申立書の作成で苦労されるかたというのが多い印象です。
年金事務所や、可能なら周囲の支援を受けながら、 遅くなってしまわないように作成を進めていくようにしましょう。
また、受診状況等証明書についてですが、 初診病院から全く転院していないような場合、初診病院が今現在通院している病院、つまり診断書を書いてくださる病院と同じ場合には、受診状況等証明書の取得は不要になります。 診断書の中に受診状況等証明書の記載内容と同じ内容が記載されるため、あえて二重に取得する必要はないということです。
そのほか、知的障害で障害年金請求を行う場合ですが、知的障害は取り扱い上、初診日が誕生日になりますので、あえてこの受診状況等証明書を取得する必要はない、ということになっていますので、覚えておきましょう。
具体的な手続きの流れ
そして、障害年金の手続きを行っていくにあたって、その具体的な作業の流れについてお話しします。
最終的に正しく手続きができれば問題はありません。ここでは一例をご紹介いたします。
<具体的手続き例>
1. 受診状況等証明書の取得(初診日の確定)
2. 診断書の取得
• 可能な限り、日常生活状況や自覚症状等を医師に伝えることがポイントです
• 完成した診断書の内容が現状にあっているか、相違点は無いかチェックする
3. 病歴・就労状況等申立書の作成
• 発病から現在に至るまでの経過を簡潔に書いていく
• 診断書の記載内容と齟齬が出ないように注意
4. 振込先通帳、マイナンバーなどの必要添付書類を揃える
5. 窓口に裁定請求書を提出
• 年金事務所
• 街角の年金相談センター
• お住まいの市(区)役所または町村役場
上記のいずれかに提出 ※役場は障害基礎年金のみ
まず最初に、受診状況等証明書の取得を行います。
初診日を確定するということになります。
時々、先に診断書を取得されてしまうかたがいるんですが、実は後で証明書の取得をしてみたら、自分の思っていた初診日と違かった、自分も忘れていたけれど、実はさらに前に違う病院の受診があったことが判明した、など、初診日の確定は、当初の予定通りに行かないことが多いです。
そんな中、先に診断書を取得してしまうと、取るべき診断書の日付が間違ってしまって、診断書の取り直しになったり、もたもたしている間に診断書の有効期限が切れてしまうといったことが起こることがあります。
障害年金の手続において、初診日は非常に重要なものになります。
ですので、まずは初診日を確定させてから、次の作業に移るようにしましょう。
次は、診断書の取得です。
障害年金で重要視されているのは、そのご病気でどれだけ生活に支障が出ているのか、ということです。
ですので、診断書を作成していただく主治医には、事前に日常生活の状況や自覚症状などを可能な限りお伝えして、診断書に反映してもらうことが大切です。
また、作成してもらった診断書は、封がしてあることが多いですが、必ず開封して中身を確認しましょう。
そして、記載に間違いがないかどうか、よく確認するようにしましょう。
提出した診断書は、必要な記載事項に漏れがない限りは、どれだけ実際の状況と齟齬があったとしても、それは正しい内容として審査が行われます。
このため、必ず記載内容を確認して、もし記載内容に相違がある場合には、事前に先生に相談をして、修正をしていただいてから提出するようにしましょう。
また、診断書は必ずコピーを取っておくようにしてください。
その後、病歴・就労状況等申立書を作成します。
申立書を作成する場合には、発病から現在に至るまでの経過を、時系列に沿って簡潔に書いていきますが、箇条書き形式で書くと内容を整理しやすく、また、読みやすいのでおすすめです。
また、なぜ、証明書や診断書の後に申立書を作成するのかということですが、証明書や診断書を見ながら申立書を作成することにより、記載内容にズレが生じることを防ぐことができるからです。
診断書などの書類と申立書の内容に相違があると、審査側からの問い合わせにつながって、審査が遅くなってしまったり、思わぬ審査結果となってしまうこともあります。
ですので、一貫性のある書類作りを心がけていくことが大切です。
ただし場合によっては、診断書を作成する病院から、先に、申立書の提出が求められることがあります。
その場合には、指示に従って先に申立書を作成して、診断書ができてきてから再調整を行うということになります。
また、先に申立書を作成して、これを主治医への情報提供として活用するということも、非常に有効です。
もし余裕があるという場合には、先に申立書を作ってみるのも良いかもしれません。
受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書が揃ったら、そのほか、年金の振込を希望する銀行口座の通帳やマイナンバーカードなどの必要な添付書類を揃えます。
必要な添付書類は、個人個人で異なってきますので、窓口担当者の指示に従うようにしましょう。
そして最後に、窓口で障害年金の請求書を提出します。
請求書類の書き方については、窓口で教えてもらいながら書くようにしましょう。
なお、障害年金の手続きができるのは、年金事務所、街角の年金相談センター、市町村役場になります。
ただし、市区町村役場は、障害基礎年金の手続きのみ対応してもらうことができます。
年金事務所、街角の年金相談センターでは、障害基礎年金、障害厚生年金の両方ともOKです。
このいずれかの窓口への提出で問題ありませんが、個人的には年金事務所もしくは、街角の年金相談センターへの相談がおすすめです。
障害年金の制度は非常に複雑です。年金以外にもたくさんの業務を行う役所では、担当者のかたが障害年金についての知識が十分ではない場合があります。
もちろん立地的にそもそも通うことができるかどうかという問題もあるかとは思いますが、もし可能ならば年金事務所もしくは街角の年金相談センターへの相談・提出をおすすめいたします。
そして提出後は、審査の結果が出るのを待つということになります。
障害年金はいつ振り込まれるのか?
•障害年金は2か月に1回、偶数月15日(休日前倒し)に2か月分が支給されます
•初回だけは奇数月に支払われることもあります
•振込先は原則本人口座のみ(後見人等は指定可)
最後に、障害年金はいつ振り込まれるのかに関して、お話しします。
まず、支給日についてご説明をいたします。
提出した書類に基づき障害年金の審査が行われて、無事認定となった場合、その後は障害年金の支給が行われることになります。
障害年金の具体的な支給日についてですが、他の年金制度と同じになり、2ヶ月に1回、偶数月の15日に2ヶ月分が支給されることになっています。
15日が土日などの金融機関の休日に該当する場合には、前倒しで支給が行われます。
また、偶数月での支給が基本ですが、認定のタイミングによっては、初回だけは奇数月の15日に支給されるという場合もあります。
ここで、2ヶ月分というのは、何月分の支給が行われているのかということですが、年金は後払い方式になっています。
具体的には、4月分、5月分が6月に支給、6月分、7月分が8月に支給、このようなサイクルが続いていきます。
障害年金の振り込み先について、ご家族の口座に振り込めないのか、というご相談をいただくことも多いですが、原則として振り込み先は、ご本人名義の口座しか指定することはできません。
もし、後見人がついているという場合には、後見人の口座を指定することは可能です。
以上、簡単にですが、障害年金の制度の概要から、必要な書類、実際の入金のサイクルまでお話をしました。
障害年金の手続きは大変なことも多いですが、少しでも皆さんの障害年金制度理解の助けになれば大変幸いです。