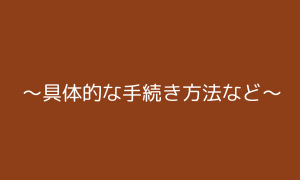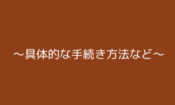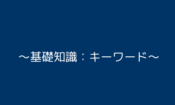STEP6:必要書類の取得と年金請求書の作成および書類提出
受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、診断書が用意できたら、必要書類を取得し年金請求書を作成して提出します。
請求時に必要な書類等は以下のとおりです。
<年金請求書>
国民年金の場合:年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号
厚生年金の場合:年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第104号
用紙は年金事務所に常備されていますので、診断書用紙などと一緒に入手しておくと便利です。
<添付書類等>
必要な添付書類は、請求の内容や請求者の状況によって異なりますし、数も多くて複雑です。
添付書類については、請求書様式にも記載されていますが、わかりにくいです。
また、記載のない書類を要求されることもありますので、事前に年金事務所でよく確認して準備を進めるとよいでしょう。

Action:年金請求書を作成しましょう。
<障害給付請求事由確認書>
障害認定日請求(遡及請求)の場合、「障害給付請求事由確認書」を提出します。
この書類を提出することにより、障害認定日の診断書で等級非該当等による不支給となっても、請求日の診断書により、事後重症請求として審査を受けることができます。
これにより、事後重症として一旦決定を受けた後に、認定日請求に関して不服申立(審査請求)をするかどうか検討することができます。
障害認定日請求(遡及請求)の場合は、「障害給付請求事由確認書」を必ず添付しましょう。
Action:障害認定日請求(遡及請求)の場合は、「障害給付請求事由確認書」を作成してください。
<年金生活者支援給付金請求書>
<年金生活者支援給付金>
2019年10月分より、1級または2級の障害基礎年金を受けている人に、障害年金と併せて「障害年金生活者支援給付金」が支給されるようになりました。
消費税10%の導入と同時に開始され、年金とは別の制度で、年金機構が支給に関わる事務を担っています。
受給するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
① 障害基礎年金を受けている
②前年の本人の所得が4,721,000円以下
※基準となる4,721,000円は、扶養親族の数、年齢などに応じ増額されます。
支給額(月額)は、以下のとおりです。
1級:6,638円
2級:5,310円
※毎年4月に、前年の物価変動に応じて金額は見直されます。
障害年金の請求時に、この給付金の申し込みも一緒にします。
Action:「年金生活者支援給付金請求書」を作成してください。
<書類の提出先>
障害基礎年金の場合は、提出先は、住所地の市区町村役場の窓口になります。
なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
障害厚生年金の場合は、提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
書類を提出する際には、提出先の窓口で不備がないかを確認してもらい、受付印を押してもらいます。
このとき、受付印が押された年金請求書の控えは、必ずもらっておきましょう。
受付印が重要なのは、事後重症で請求して支給決定となった場合、受付印の日付の翌月から障害年金が支給されるためです。
また、年金請求書の控えは、年金請求をした証拠書類ですから、提出書類のコピーと一緒に大切に保管しましょう。
Action:各提出書類について最終チェックを行い、年金事務所等に提出しましよう。
★各提出書類等は、必ずコピーを取っておいてください。
年金手帳や預金通帳は返却されますが、障害年金請求書、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書等は返却されません。そのため、提出前に必ず各書類のコピーを取っておくことが大切です。
各書類のコピーは、後日、結果が不支給となった場合、不支給となった原因を探したり、審査請求の対策を講じる際の重要な資料となります。
また、給付が認められた場合でも、有期認定の場合には、数年後に現況届と診断書の提出が求められます。その際に、障害の状態は変わっていないにもかかわらず、診断書の記載内容が変化してしまうことがあります。そのような場合にも、新たに取得した診断書の内容について、最初の障害年金請求時の診断書を参照し、比較等を行い精査することができます。