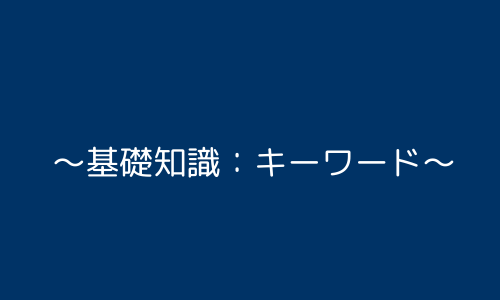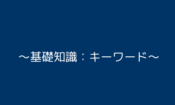精神の障害に係る等級判定ガイドライン
平成28年9月1日より、精神障害(てんかんを除く)の等級判定については、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づき審査が行われることになりました。
検査数値等の客観的な基準を設けにくい精神障害や知的障害などでは、等級の判定に地域差が生じていました。
この問題を解消するために設けられたのが、このガイドラインです。
ガイドラインでは、等級判断のバラツキを解消するため、診断書記載事項と障害等級との関係性を、まず数値で示し、数値化できない記載事項については、等級判定への考慮方法を明確にしています。
具体的には、マトリックス表で等級の目安をつけ、5つの要素を勘案して総合的に等級認定が行われる仕組みとなっています。

<考慮すべき5つの要素>
1現在の病状又は状態像
2療養状況(外来・入院の状況、治療歴など)
3生活環境(同居人の有無、福祉サービス利用状況など)
4就労状況
5その他(精神障害者保健福祉手帳の有無・等級など)
<等級目安の認識例>

マトリックス表の日常生活能力の程度は、診断書(精神の障害用)の項目「日常生活能力の程度」の番号(5段階)で、障害の程度は、数字が大きいほど重度となっています。

マトリックス表の日常生活能力の判定平均は、診断書(精神の障害用)の項目「日常生活能力の判定」7項目を数値化(4段階:左端を1、右端を4)し算出した平均値です。(チェックの入った項目の数値の合計を、7で除して算出)
左図の例では、各項目の数値の合計は23で、平均値は3.2(=23÷7)となります。
上図の例では、「日常生活能力の程度」が(4)、「日常生活能力の判定」7項目の平均値が3.2となります。
マトリックス表で、日常生活能力の判定平均の行と程度の列の交わるところを確認すると、2級の目安であることがわかります。